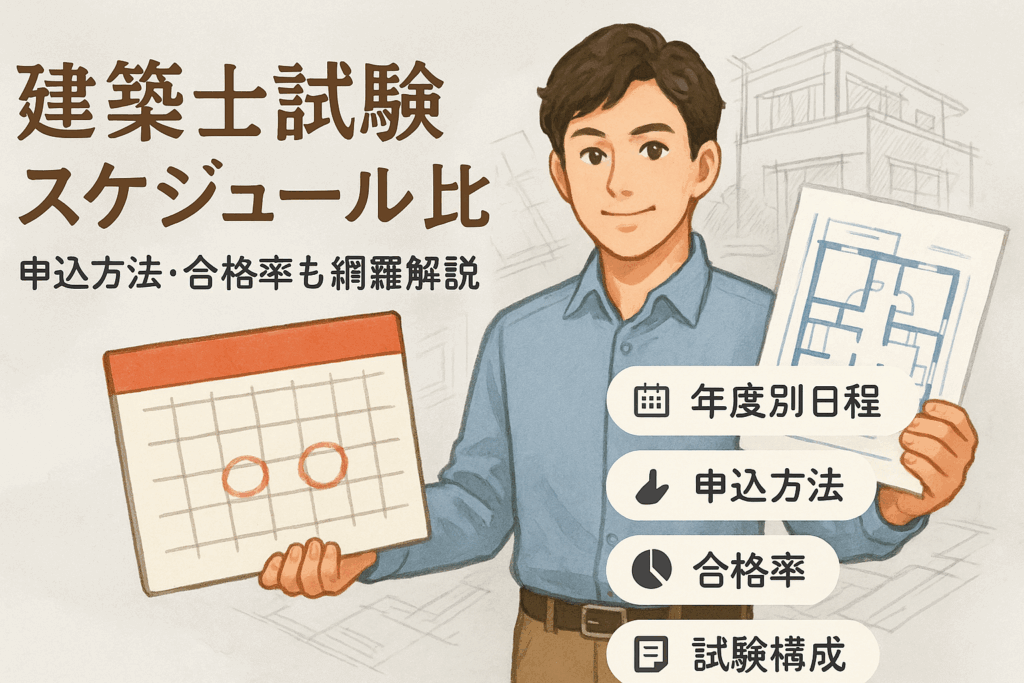建築士試験の日程は、毎年の発表直後から検索が急増するほど、受験者にとって重要なポイント。「学科試験は例年7月上旬」「設計製図試験は9月頃」「二級建築士試験は6月と9月」など、日程の違いや、令和表記と西暦表記の混在による混乱で、「うっかり申込を逃してしまう」「直前に気づいて焦る」といった声も少なくありません。
新制度への移行や、近年は自然災害・感染症の影響による日程変更・イレギュラー開催も実際に生じています。令和3年(2021年)には台風接近で一部試験会場の日程変更が行われました。正確なスケジュール把握と、年度ごとの傾向比較は合格のための学習計画や仕事との両立でも不可欠です。
「日程を見落とすリスクを回避したい」「自分に合った準備スケジュールを立てたい」と感じている方へ。この記事では、最新の【2025年版】一級・二級建築士試験の全スケジュール比較、重要な申込日程、過去の変更情報の注意点まで網羅。最後まで読むことで、確実なスケジュール管理と効率的な合格戦略が手に入ります。
建築士試験の日程は全体像と年度別スケジュール比較
建築士試験は一級建築士試験および二級建築士試験に分かれ、出題範囲や試験日程が異なります。両試験とも例年、学科試験は夏に、設計製図試験は秋から冬にかけて行われます。年度による日程の違いにも注目が必要です。
| 試験区分 | 2024年 | 2025年 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 一級建築士 学科 | 7月21日 | 7月20日 | 全国統一、午前午後制 |
| 一級建築士 製図 | 10月13日 | 10月12日 | 学科合格者が対象 |
| 二級建築士 学科 | 7月7日 | 7月6日 | 制度・法規中心 |
| 二級建築士 製図 | 9月15日 | 9月14日 | 設計実務力重視 |
このように、毎年7月に学科、9~10月に製図が設定されています。下記で年間の流れや直近の変化も取り上げます。
一級建築士試験と二級建築士試験の日程体系の理解
一級建築士と二級建築士では、受験資格や試験内容のほか試験日も異なります。特に令和6年(2024年)、令和7年(2025年)、さらにその翌年へとスムーズに移行する方式をとります。
| 項目 | 一級建築士 | 二級建築士 |
|---|---|---|
| 試験日受付 | 例年4月 | 例年3~4月 |
| 学科試験 | 毎年7月中旬 | 毎年7月上旬 |
| 製図試験 | 毎年10月中旬 | 毎年9月中旬 |
| 合格発表 | 12月 | 12月 |
両試験とも受付期間・申込開始日に差があり、出願時の顔写真要件や試験会場も異なります。合格率については一級建築士が約8~15%、二級建築士は20%前後で推移しています。
試験日程の季節や時期別分類とスケジュール管理のポイント
建築士試験の学科は夏、製図は秋から冬への開催が基本です。スケジュール管理のコツを挙げます。
-
早めの学習開始:申込み開始から最短でも3~4カ月前の学習スタートが効果的
-
模試受験時期:学科試験の約1~2カ月前を目安に模擬試験を受けると効果的
-
受検票や会場確認:受検票は学科試験2~3週間前に発送されますので、会場情報は事前確認を
| 時期 | 重要ポイント |
|---|---|
| 申込直後~ | 学習計画策定 |
| 4月~6月 | 受験票到着・会場確認 |
| 7月 | 学科本番・自己採点 |
| 9~10月 | 製図試験対策・本番 |
近年の日程変更やイレギュラー開催について
社会的な影響や災害による試験日程の変更事例も近年増えています。2020年には新型感染症への対応として一部の試験で日程延期や会場変更が実施されました。
-
大規模災害時:会場ごとの開催延期や代替日設定が行われる場合があります
-
感染症流行時:受験生の安全確保のため定員制や分散開催、日程再設定などの例も
-
公式発表の確認:突発的な変更に備え、必ず公式サイトや試験機関からのお知らせを確認してください
例年通りで進行している場合も油断せず、最新の日程や試験要綱は必ずチェックして、余裕を持ってスケジュール管理を行ってください。
一級建築士試験の日程の詳細と申込スケジュール管理法
一級建築士学科試験の日程・開始時間と終了時刻の詳細
一級建築士学科試験は年1回開催され、2025年度は7月13日に実施される予定です。試験は午前と午後に分かれており、スタート時間は午前9時30分、終了は17時40分前後となります。
主要な科目ごとの時間割は以下の通りです。
| 区分 | 開始 | 終了 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 学科Ⅰ | 9:30 | 10:50 | 計画 |
| 学科Ⅱ | 11:10 | 12:30 | 環境・設備 |
| 学科Ⅲ | 13:30 | 15:10 | 法規 |
| 学科Ⅳ | 15:30 | 16:40 | 構造 |
| 学科Ⅴ | 17:00 | 17:40 | 施工 |
時間割に余裕があるため、各セクション間には10~60分の休憩が設けられています。効率的な時間配分が合格へのカギとなります。
受験申込受付期間と受験票発行スケジュールの完全解説
受験申込はインターネットでのみ受付けており、2025年の申込期間は4月1日から4月15日までです。早めの手続きが推奨されます。
手続きの流れは次の通りです。
- 公式サイトで受験申込の登録
- 必要書類・顔写真データのアップロード
- 受験料の支払い
- 登録内容の確認・申請
受験票は6月中旬にWeb発行され、マイページからダウンロード・印刷が必要です。顔写真のアップロード不備や期日遅れによる受付不可例が少なくないため、細心の注意が求められます。
設計製図試験の日程、課題公表から合格発表まで
設計製図試験は9月14日に実施予定で、課題は7月下旬に公式発表されます。合格発表は12月25日に行われる予定です。
課題発表から試験当日まで約2か月間の準備期間があるため、過去課題の分析や実務的なスキル確認が重視されます。
課題内容は毎年異なり、現行法令や設計手法の知識も問われます。
試験当日のタイムスケジュールと持ち物リスト、当日注意点まとめ
設計製図試験当日の流れは下記の通りです。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 9:00 | 集合・着席受付開始 |
| 9:30 | 試験説明 |
| 10:00 | 試験開始 |
| 17:00 | 試験終了 |
必要な持ち物は以下のリストで確認できます。
-
受験票
-
公的身分証明書
-
製図用具一式(定規・三角スケール・製図ペン等)
-
指定課題用紙
-
昼食・飲料水
-
時計(携帯等の通信機器は不可)
会場では遅刻や忘れ物、机上の資料持ち込みなどの規定違反に厳しく対応されます。万が一遅刻・体調不良等が生じた際はすぐに監督員へ連絡しましょう。必ず公式の注意事項を事前に確認し、安心して受験日を迎えてください。
二級建築士試験の日程と申込の具体的流れ
二級建築士試験日と科目別試験時間割の詳細情報
二級建築士試験は、学科試験と製図試験の2段階構成です。学科試験は一般的に7月中旬、製図試験は9月上旬に実施されます。学科試験の時間配分や問題形式は下表の通りです。
| 科目 | 出題形式 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 計画 | マーク式 | 60分 |
| 法規 | マーク式 | 60分 |
| 構造 | マーク式 | 60分 |
| 施工 | マーク式 | 60分 |
| 学科総合 | マーク式 | 210分 |
ポイント
-
各科目はマークシート式で実施
-
試験は一日にまとめて行われる
-
学科合格後に製図試験への進出が可能
適切な時間配分と科目ごとの特性を押さえることが重要です。
二級建築士申し込み期間・受付方法と受験票の発行詳細
二級建築士試験の申込期間は例年4月~5月上旬に設定されます。インターネットによる申請が基本で、紙での受付はごく一部です。下記は申込の流れです。
申込フロー
- 公式サイトから申込ページにアクセス
- 必要事項を入力し、顔写真データをアップロード
- 受験料の支払い(クレジットカード等可)
- 期間内に申し込み完了メールが届く
- 受験票は6月中旬以降に郵送またはWEB上で発行
注意点
-
写真サイズやデータ形式の不備に注意
-
期日を過ぎると受付不可となるため、申請は余裕を持って行いましょう
製図試験日程と対策上重要な課題発表タイミング
製図試験の本番は、例年9月上旬に行われます。課題発表は学科試験の合格発表と同時、7月下旬が多い傾向です。合格発表直後に課題を確認し、計画的な準備に入ることが合格への近道です。
| 製図課題発表 | 製図試験日 |
|---|---|
| 7月下旬 | 9月上旬 |
課題発表後の過ごし方
-
課題内容を分析
-
過去の出題傾向を確認
-
実務経験や演習で自信を深める
製図準備期間は約1カ月強。効率良くスケジュールを立てて進めましょう。
二級建築士の試験当日の流れ・持ち物・受験会場事情
試験当日は時間に余裕を持ち、最寄りの会場へ向かいます。持ち物の忘れものが無いよう下記リストを活用してください。
持ち物リスト
-
受験票
-
本人確認書類(免許証など)
-
筆記用具(複数本のシャープペンシル/消しゴム)
-
時計
-
製図用具一式(定規、コンパスなど)
会場は全国主要都市に設定されているため、アクセスしやすい立地が中心です。試験開始30分前には着席を済ませ、試験監督の指示に注意しながら進行してください。遅刻や忘れ物防止がスムーズな受験のポイントです。
建築士試験の日程における申込方法の詳細ガイドと注意点
申込受付期間や方法(ネット受付の詳細と郵送手続き)
建築士試験の申込受付期間は毎年決まった時期に設定されており、インターネット受付が主流です。申込期間中に公式サイトの専用フォームから必要事項を入力し、事前に用意した顔写真データをアップロードして手続きを進めます。手続きが完了すると、申込完了メールが届きます。万が一、ネット環境がない場合や、インターネット申込に不具合が生じた場合には、郵送による申請も可能です。
郵送の場合は、所定の申込書類をダウンロードし記入の上、証明写真や必要書類を同封して指定先に送付します。インターネット申込・郵送ともに期日厳守が求められます。申込終了間際はアクセスが集中しやすいため、余裕を持って手続きを完了することが重要です。
下記テーブルに主な受付方法をまとめました。
| 申込手段 | 必要なもの | 注意点 |
|---|---|---|
| インターネット | 顔写真データ、メールアドレス | タイムアウト・データ不備 |
| 郵送 | 証明写真、申込書、各種証明書類 | 書類不備・消印有効日確認 |
申込時の顔写真や書類の規格・アップロードのポイント
提出する顔写真は、規定サイズと解像度・背景色が厳格に定められています。一般的に、6か月以内撮影の上半身正面・無帽・無背景が条件であり、パスポート用写真と似た形式です。デジタルデータの場合は、JPEG形式、指定されたピクセル数やファイル容量を必ず満たしてください。
オンライン申請時はアップロードエラーの発生が多いため、写真データのファイル名や容量、画像の鮮明度を事前にチェックしましょう。不鮮明な画像や容量超過、規格外のサイズでは申請を受理されません。郵送の場合でも、写真の裏面に氏名・受験区分を記載するなど細かな指定があるため、案内をよく確認してください。
書類データや証明書(卒業証明・実務経験証明等)も、指定フォーマットでアップロード・郵送が必要です。書類不備や形式ミスによる受付不可が多発するため、提出前に複数回チェックすることをおすすめします。
過去によくある申込ミス例とその防止策
申込ミスは毎年多く発生しており、特に写真規格・書類不備・入力ミスによるトラブルが目立ちます。よくあるミスの例とその防止策をリストでご紹介します。
-
写真規格ミス(背景色やサイズ違いなど)
-
メールアドレスや個人情報の入力間違い
-
卒業証明・実務経験証明書の添付モレ
-
受付期限のうっかり忘れ
-
デジタルファイル名の全角・記号利用
これらを防ぐためには、強調しておきたいセルフチェックが重要です。
- 受付期間・締切日をカレンダーやスマホに登録して事前アラートを設定
- 写真データチェックリストを作成し、要件と照合
- 書類提出前に家族や同僚、第三者によるダブルチェック
- オンライン申込後は「申込完了メール」を保管し進行状況を随時確認
ポイントのセルフチェックリストを活用することで、スムーズな申込完了につながります。
| ミスの種類 | 主な内容 | 防止策 |
|---|---|---|
| 写真規格不一致 | 背景・サイズ・解像度が異なる | 要件リストで事前確認 |
| 情報入力エラー | 氏名やメールアドレスの誤入力 | 送信前の見直し必須 |
| 書類添付漏れ | 卒業証明や実務証明の不足 | チェックリストで徹底確認 |
| 期限内未手続き | 締切を過ぎて申請不能 | カレンダー登録 |
建築士試験の日程に伴う合格率や難易度推移の詳細分析
一級建築士試験の合格率・合格点・難易度を時系列で追う
一級建築士試験は数ある資格試験の中でも難易度が高く、合格率は各年度によって違いがあります。過去数年の合格率は概ね10%前後で推移しており、2024年度も約10.5%と厳しい水準となっています。試験は学科と設計製図で構成され、それぞれの合格点が毎年設定されます。学科は総合的な建築知識が必要で、過去5年の学科の合格点はおおむね90点前後(満点125点)で推移しています。設計製図では採点基準の改定が行われたこともあり、試験対策にも適応が求められています。難易度は実務経験や専門知識が問われ、長時間の学習と精密な理解が不可欠です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 学科合格点 | 製図合格点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26,518 | 3,866 | 14.6% | 90 | ー |
| 2023 | 25,314 | 3,627 | 14.3% | 90 | ー |
| 2024 | 24,700 | 2,594 | 10.5% | 90 | ー |
合格率が低い背景には専門性の高さと、合格点到達には体系的な実務経験が必要なことが挙げられます。
二級建築士試験の合格率と難易度の特徴や傾向
二級建築士試験は一級に比べ受験者数が多く、合格率は20%~30%ほどで推移しています。試験の構成や日程は一級と似ていますが、対象となる建築物の範囲が異なるため、問われる知識や確認項目がやや異なります。2023年の合格率は約24%、2024年は約22.5%となっており、難易度は一定の水準が維持されています。
試験内容は近年少しずつ改訂されており、法改正などに応じて出題分野が見直されるため、最新の試験傾向を把握しておくことが重要です。合格には学科・設計製図双方のバランスが求められるため、計画的な勉強が必要です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,675 | 7,934 | 23.6% |
| 2023 | 32,800 | 7,972 | 24.3% |
| 2024 | 31,500 | 7,087 | 22.5% |
合格率と日程や試験内容の関係性の考察
建築士試験の日程や実施方法は合格率に一定の影響を及ぼします。受験者数が多い年度や大きな制度改正があった年は合格率が変動しやすく、特に学科試験の時期や問題傾向の変更が大きな要因となります。近年はインターネット申請や申込期間の短縮などが見られ、受験準備の効率化が進められています。
また、試験内容の改定は合格率にも連動しており、設計製図試験の変更点や法規制の新設により、対応を誤ると合格率は低下します。下記のような要因により、合格しやすい年・難しい年が生じやすいのが特徴です。
-
法改正や制度変更による出題内容の変動
-
試験日程や受験準備期間の長短
-
受験資格や実務経験要件の見直し
-
オンライン申込等の利便性改善
これらの観点を踏まえ、常に最新情報を確認し準備を進めることが建築士試験合格への近道となります。
建築士試験の日程と会場情報および地域別受験環境ガイド
全国主要会場の一覧と受験地選択のポイント
建築士試験は、全国各地の指定会場で実施されます。都道府県ごとに設けられている主要試験会場の一部を以下の表にまとめました。会場選びは交通アクセスや混雑状況、居住地からの移動時間などを考慮することが大切です。不慣れな場所だと当日の移動が負担になるため、できるだけ慣れ親しんだ地域を選択するとよいでしょう。
| 地域 | 主な試験会場名 | アクセスの特徴 |
|---|---|---|
| 東京 | 東京ビッグサイト、明治大学 | 鉄道やバスが充実 |
| 大阪 | 大阪工業大学、大阪ビジネスパーク | 新幹線・都市鉄道が便利 |
| 愛知 | 名古屋工業大学 | 市内アクセス良好 |
| 北海道 | 北海道大学、札幌市教育文化会館 | 地下鉄・JRが利用可能 |
| 福岡 | 九州大学、アクロス福岡 | 空港や新幹線も至近 |
| 宮城 | 東北大学、仙台国際センター | 東北新幹線でアクセス可 |
受験地選択のポイント
-
自宅や職場からの距離・交通手段の利便性
-
会場周辺の混雑具合や宿泊先の確保
-
当日の天候や季節要因も考慮して余裕を持つ
受験地による特徴や試験当日の混雑・交通事情の違い
首都圏や大都市圏の試験会場は、多くの受験者が集中するため、試験当日は公共交通機関や現地までの道路が非常に混雑する傾向があります。首都圏では朝のラッシュと重なる場合も多いため、予定より早めの出発や複数パターンのルート確認が重要です。
地方の会場は比較的人が少ないものの、バスや鉄道の本数が限られているケースもあるため、事前に時刻表をしっかり確認しておきましょう。特に冬場は天候の変化にも注意が必要です。
試験当日の移動・混雑対策のポイント
-
最寄り駅や乗り換え駅までの経路を事前調査
-
交通系ICカードのチャージ・定期券の準備
-
万が一の遅延や天候悪化に備え宿泊前泊も検討
-
開始時刻前の余裕ある到着を心掛ける
試験会場選択変更の可能性と申請手続きの留意点
定員超過ややむを得ない事情で会場を変更する場合、公式な申請手続きが必要となります。会場ごとに定員が設定されており、希望する日時に申請しないと希望会場が選べないこともあります。会場変更を希望する場合は、具体的な締切日や申請方法(オンライン・郵送など)を公式情報で必ず事前確認してください。
会場枠が埋まると自動的に受付終了となり、他の近接会場が案内される場合もあります。手続きに不備があると受験票発行に支障が出ることがあるので、申請時は入力内容や必要書類に十分注意しましょう。
会場変更時の注意点
-
申請期間や方法を公式で最新確認
-
必要書類や手続きミスに要注意
-
万一のトラブル時は速やかに運営窓口へ連絡
どの会場でも試験当日は余裕を持った行動が合格への第一歩です。
建築士試験の日程から考える効果的な学習計画と合格戦略
試験日を起点に組む年間や短期・直前学習スケジュール例
建築士試験の日程を十分に把握し、学習計画を緻密に立てることが合格への近道です。まず試験の年間スケジュールを確認し、逆算して準備を進めましょう。特に一級建築士試験や二級建築士試験の申込期間や試験日変更の有無には常に注意が必要です。
年間の学習計画の例としては、下記のような流れが効果的です。
-
学科試験まで6ヶ月〜12ヶ月: 基礎知識の徹底理解と過去問演習
-
試験3ヶ月前〜1ヶ月前: 苦手分野の集中対策と予想問題演習
-
直前期1ヶ月: 重要ポイントの総復習と時間配分のシミュレーション
-
試験当日: 必要書類や持ち物チェック、リラックスした状態での本番対策
また、試験日程の詳細や最新情報は常に公式発表をチェックして、予定変更にも素早く対応できるようにしておきましょう。
合格率や難易度データを活かした継続学習のコツ
建築士試験の合格率や難易度を知ることで、現実的な学習計画を練ることが可能です。一級建築士の合格率は例年10%台、二級建築士でも20%台と、いずれも高い専門性が求められます。合格への最大のコツは継続学習ですが、以下のポイントを意識すると効率が上がります。
-
客観的データの活用: 合格率や得点分布を把握し、重点分野の学習計画に反映
-
学習進捗の可視化: 進捗管理シートやアプリで日々の学習状況を確認
-
学習モチベーションの維持: 継続的な小目標の設定と自己評価
-
定期的な自己テスト: 過去問・模擬試験による知識定着確認
下記のテーブルで一級・二級建築士試験の例年合格率と主な難易度指標を紹介します。
| 区分 | 主な試験日 | 合格率(例年) | 難易度概観 |
|---|---|---|---|
| 一級建築士 | 7月・10月 | 10~13% | 非常に高い |
| 二級建築士 | 7月・9月 | 20~25% | 高い |
合格率の高さ・低さではなく、日々の積み重ねと計画的な学習が結果につながります。
試験日程の急変時に備えた柔軟な計画修正方法
急な試験日程変更や予期しないスケジュール変更が発生した場合でも、柔軟に学習計画を再構築できる姿勢が重要です。特に近年は自然災害や社会情勢による日程変更ケースも見受けられます。
-
最新の試験情報を確認: 公式サイトで日程や会場変更速報を常に確認
-
計画の見直しリストを作成: 新しい日程に合わせて短期・中期目標を再設定
-
無駄な焦りを排除: 必要情報だけを整理し、焦らず落ち着いて行動
-
学習リズムの保ち方: 変更後の期間を活用した新たな習慣づくり
重要なのは、どのような事態でもすぐに予定を組み直し、合格への努力を継続することです。不測の事態にも適応できる準備と心構えが、合格への確かな後押しになります。
建築士試験の日程に関する重要確認事項や最新情報の入手方法
2025年最新版の試験日程ハイライトと公式情報確認ポイント
建築士試験の2025年版スケジュールは毎年変動があるため、誤った情報には十分注意が必要です。公式発表を確実に把握するためには、公益財団法人建築技術教育普及センターの公式サイトや、各都道府県の建築士会の案内を定期的に確認しましょう。最新の日程や時間、試験区分ごとの違いを比較できるよう、主要な項目をテーブルに整理します。
| 試験区分 | 学科試験日 | 製図試験日 | 申込受付期間 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|
| 一級建築士 | 2025年7月13日 | 2025年9月14日 | 2025年4月1日~15日 | 2025年12月15日 |
| 二級建築士 | 2025年7月20日 | 2025年9月21日 | 2025年4月1日~15日 | 2025年12月22日 |
主な情報取得時の注意点
-
公式情報は毎年更新されるため、年度を間違えないようにする
-
インターネット申込の場合は受付時間やシステムメンテナンス時間にも注意
-
詳細な試験内容や会場一覧も併せて確認しておく
このように複数の信頼できる公式情報源を使い分けることで、予定の大きなズレを防げます。
申込直前や試験直前に再チェックすべき日程関連注意事項
申込や試験当日にはうっかり忘れがちな注意事項も多く、必ずチェックリストを活用しましょう。特に日程や会場情報、必要な持ち物、申し込み書類の不備がないか最終確認が不可欠です。
再チェックすべき重要ポイント
-
申込締切日と受付期間の終了時刻(例:2025年4月15日 17:00まで)
-
顔写真データのアップロード要件(サイズや背景色など)
-
受験票・必要書類の印刷と持参物の準備
-
会場の正式名称とアクセス方法
-
学科試験・製図試験の開始時間、集合時間
-
天候や交通トラブルなど緊急時の連絡先
強調ポイント:
申込ミスが合格機会の損失につながるため、下記のリストで再確認を徹底してください。
- 公式申込ページに従い入力ミスや漏れがないか見直す
- 支払完了後、申込受付完了通知を必ず確認する
- 申込後の変更やキャンセルの可否も事前に確認
定期的な再チェックが、トラブルを回避し合格への近道となります。余裕を持ったスケジュール管理を意識しましょう。
公式サイトや通知を活用した最新情報収集の習慣化
最新の建築士試験の日程や時間割、申込情報を見逃さないためには、公式発表を確実にキャッチできる環境を整えることが重要です。
日々の情報収集ポイント
-
公益財団法人建築技術教育普及センターの公式サイトで最新発表を習慣的に確認
-
メール通知や公式SNS機能を使い、自動で発表を受け取れる設定を行う
-
受験生向けの公式LINEやその他SNSに登録し、期日直前のリマインダー機能を活用
-
各都道府県ごとの会場案内も定期的にチェック
習慣化のコツ:
リマインダーアプリやカレンダー機能を活用し、締切や試験日を事前に通知する工夫がおすすめです。情報の見逃し・申込忘れを防ぐため、家族や友人と日程を共有する方法も効果的です。
確実な合格を目指すなら、日々の最新情報収集と段階ごとの再確認が不可欠です。