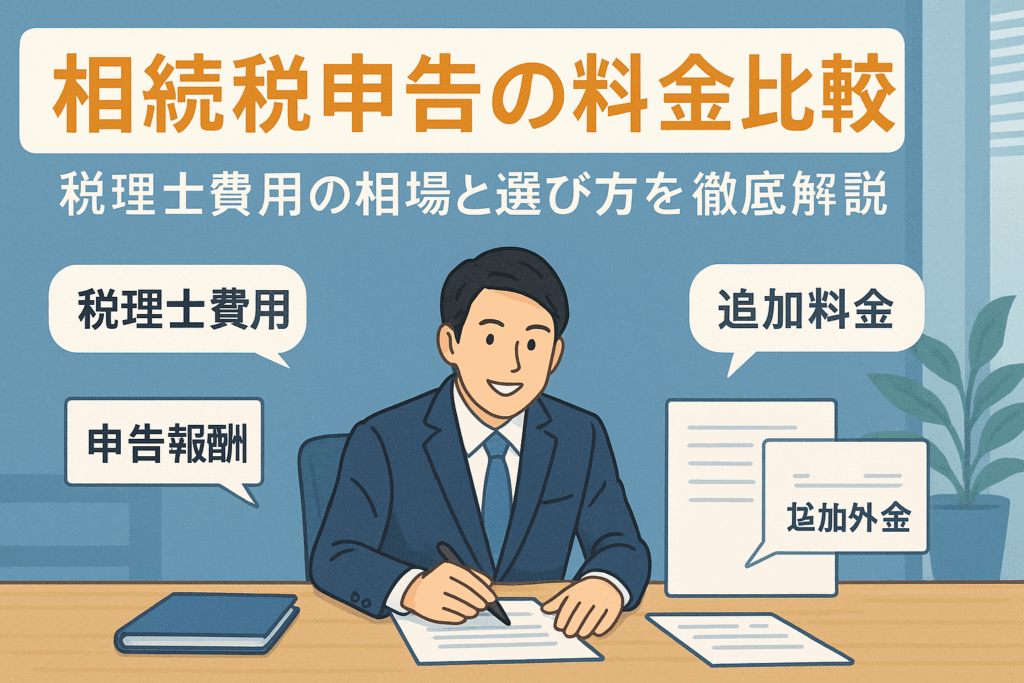相続税申告の料金表は「遺産総額の0.5~1%が相場」と言われていますが、実際の負担額は相続人の人数や土地の評価、特急申告の有無などによって大きく変動します。たとえば遺産総額5,000万円の場合、税理士報酬の基本料金はおよそ25万円から50万円が現実的な目安です。さらに土地を複数所有していたり、相続人の人数が増えると加算報酬が発生し、費用が増加するケースも少なくありません。
近年は【2025年分の路線価改定】の影響で、都市部を中心に土地評価額が上昇し、税理士料金にも反映されやすくなっています。「想定外の追加費用に驚いた…」「どこまでが基本料金なのか分からない」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
「この手続き、結局いくらかかる?」という疑問を、具体的な料金表・比較事例とともに徹底解説します。最新データや実務経験をもとに、相続税申告の費用で損しないための情報をまとめました。
最後までご覧いただくと、あなたにとって最適な料金相場と、信頼できる依頼方法が分かります。今後の相続手続きでムダな出費を防ぎたい方は、ぜひ続きをお読みください。
相続税申告の料金表の基礎知識と2025年最新傾向
相続税申告の重要性と税理士利用のメリット – なぜ税理士に依頼するのか、申告の複雑さとリスクを整理
相続税申告は法律や税制の専門知識が要求されるため、多くの方が税理士のサポートを選択しています。申告には多岐にわたる書類作成や、不動産や預金の評価、控除の適用、有利な特例の活用が不可欠です。これらを個人で対応する場合、記載ミスや申告漏れが発生しやすく、税務調査や追徴課税といったリスクも懸念されます。税理士に依頼することで、正確な申告や節税のアドバイスを受けられ、安心して手続きを進められます。
依頼時の主なメリットは以下の通りです。
- 正しい相続税額の計算とアドバイス
- 節税特例や控除の適用漏れ防止
- 面倒な関係機関との調整や書類作成の代行
- 税務調査リスクの低減
特に複数の不動産や非上場株式、贈与歴などがある方は、専門家のサポートが不可欠です。
2025年最新版の相続税申告の料金表の実態 – 遺産総額別の最新相場・平均価格の詳細解説
2025年現在、相続税申告の料金は主に「遺産総額」に応じて変動します。多くの会計事務所や税理士事務所ではわかりやすい料金表を公開しています。
| 遺産総額 | 税理士報酬目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 3,000万円以下 | 20万円~30万円程度 | 基本報酬、加算なしが主流 |
| 5,000万円以下 | 30万円~45万円程度 | 相続人・評価項目で変動あり |
| 1億円以下 | 40万円~60万円程度 | 複雑な評価の場合加算あり |
| 1億円超~2億円 | 70万円~100万円程度 | 加算報酬要確認 |
| 2億円超 | 個別見積もり | 特殊案件の扱いが増える |
多くの事務所で、料金は「相続税申告書作成・提出」の基本業務が含まれていますが、下記の場合には追加料金が発生することがあります。
- 相続人や遺産分割協議が多いケース
- 名義預金の判定や非上場株式評価など特殊案件
- 特急対応希望の場合
また、報酬の支払いは相続人全員で負担するのが一般的です。複数社の料金表を比較し、内容やサポート範囲も確認しましょう。
相続税路線価の変動が料金表に与える影響 – 令和7年分路線価の概況と料金算出への影響
相続税の評価額は、毎年発表される路線価によって算出されます。2025年(令和7年)の路線価は地価動向の影響を受け、一部地域で上昇傾向が見られます。評価額が高くなると必然的に遺産総額が増し、その分、税理士の報酬も増加する可能性があります。
| 年度 | 全国平均変動率 | 路線価上昇対象地域 |
|---|---|---|
| 令和6年 | +1.2% | 都市部、主要地方都市 |
| 令和7年 | +1.5%(予測) | 東京・名古屋・福岡など |
路線価の変動により、申告額や料金表の基準金額が変更される場合があります。不動産を多く所有している場合は、最新の路線価情報をもとに税理士と相談し、料金見積もりや費用シミュレーションを行うことが大切です。加えて、今後の税制や制度改正動向もチェックし、最適な申告プランを考えることが安心かつ合理的な対応につながります。
税理士報酬の内訳詳細:基本報酬・加算報酬・オプション別解説
基本報酬の計算方法と相続財産別料金表 – 遺産総額別に詳しい料金範囲と相場解説
相続税申告にかかる税理士の基本報酬は、相続財産の総額に応じて設定されるのが一般的です。多くの事務所が遺産総額ごとに料金表を提示しており、透明性を重視しています。以下に主要な相場と目安を示します。
| 遺産総額 | 基本報酬の相場 |
|---|---|
| 〜3,000万円 | 15万円〜25万円 |
| 3,000万円〜5,000万円 | 20万円〜35万円 |
| 5,000万円〜7,000万円 | 25万円〜45万円 |
| 7,000万円〜1億円 | 35万円〜60万円 |
| 1億円〜 | 50万円〜100万円以上 |
強調ポイントとして、相続税申告の料金表は「遺産総額×0.5〜1%」が一つの目安となります。また、事前見積もりが可能なため、納得して依頼できる仕組みが整っています。
加算報酬の発生条件と費用目安 – 相続人増加や土地評価、非上場株式評価などの加算例
基本報酬に加え、複雑な状況や追加作業が必要な場合には加算報酬が発生します。発生しやすい主な加算条件は以下の通りです。
- 相続人の人数が多い場合
- 土地評価箇所が複数ある場合
- 非上場株式の評価
- 名義預金など資産調査が複雑な場合
- 緊急・特急対応依頼
相場の目安としては、相続人1人追加ごとに5万円前後、土地1筆ごとに3万円〜、非上場株式の評価で10万円以上の加算が一般的です。以下の比較表に代表例をまとめました。
| 加算要素 | 追加報酬の目安 |
|---|---|
| 相続人追加(1名ごと) | 5万円前後 |
| 土地評価(1筆ごと) | 3万円〜10万円 |
| 非上場株式の評価 | 10万円〜30万円以上 |
| 特急対応 | 基本報酬の2〜3割増し |
加算の有無や金額は事務所ごとに異なるため、見積もり時に必ず確認することが大切です。
オプションサービス料金と成功報酬の特徴 – 還付サービスや特急対応時の料金体系
料金表以外にも、オプションや成果報酬型のサービスを提供する事務所も増えています。代表的なオプションと費用は次の通りです。
- 還付申告サポート: 既納分から還付が発生する場合、還付額の20%前後が成功報酬として設定される例が多いです。
- 遺産分割協議書作成支援: 3万円〜10万円程度
- 必要書類の取得代行: 1通あたり数千円〜
- 特急対応: 基本報酬の2〜3割増しで最短数日対応
これらのオプションは柔軟に選べるため、必要なサービスだけを選択して依頼することも可能です。無料相談や報酬シミュレーションが可能な事務所も多く、費用負担を事前に明確化できる点が利用者の安心材料となっています。
相続税申告の料金表の賢い比較と失敗しない税理士選びのポイント
料金表の見方と比較時に注目すべきポイント – 総額だけでなく含まれるサービス・加算内容の比較法
相続税申告の税理士報酬は、遺産総額に比例して決まるケースが多く、全国的な相場は0.5~1%前後といわれています。しかし、料金表の総額だけでなく、どのサービスが含まれているのかをしっかりと確認することが重要です。たとえば、土地評価や非上場株式の評価、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、税務調査対応などの対応範囲で料金が異なります。加算料金が生じるケース(急ぎの申告、相続人が複数、財産が多岐)についても明確な説明がある税理士を選ぶと安心です。
料金比較のチェックポイント
| チェック項目 | 比較ポイント |
|---|---|
| 基本料金 | 遺産総額×報酬率の明示 |
| サービス内容 | 申告書作成、評価、書類取得など含む範囲 |
| 加算報酬 | 特急対応、複雑な財産構造、相続人追加での加算 |
| 見積り後の追加料金 | 最終的な負担額の変動有無 |
料金表はサービス内容や条件ごとの差が大きいため、内容の内訳まで必ず比較しましょう。
無料相談の活用法と信頼できる税理士の探し方 – 相談内容・対応スピード・口コミの重要性
無料相談を活用することで、具体的な費用感や自分に合う税理士かどうかの判断ができます。初回相談時には、事前に遺産総額や財産の内容、家族構成などの情報を整理しておくとスムーズです。また、相談時の説明のわかりやすさや見積りの明確さ、対応の丁寧さは信頼できるかどうかの重要な判断材料となります。
信頼できる税理士選びのポイント
- 相談時の質問に丁寧かつ的確に答えてくれる
- 料金体系が説明資料や書面で明示されている
- 口コミや紹介、過去の実績で評判が高い
- メールや電話での対応スピードが速い
気になる点や不安があれば遠慮せず確認しましょう。また、料金が安いだけではなく、アフターフォローの充実や専門知識の豊富さも大切です。
他専門家(司法書士・行政書士)との料金比較 – 相続手続きに関わる他職種料金のポイントと違い
相続に関わる専門家は税理士だけではありません。司法書士や行政書士も相続業務を担いますが、対応範囲と料金体系が異なります。
| 専門家 | 主な担当業務 | 一般的な料金の目安 |
|---|---|---|
| 税理士 | 相続税申告、税務相談 | 遺産総額の0.5~1% |
| 司法書士 | 不動産名義変更 | 3万~10万円(1件あたり) |
| 行政書士 | 遺産分割協議書作成など | 3万~10万円(書類1通あたり) |
税理士は税金の計算と申告が専門で、節税相談や税務調査の対応も受けられます。司法書士は主に不動産登記、行政書士は書類作成のサポートが中心です。依頼内容に応じて、必要な専門家を選ぶことが適正なコスト管理につながります。各士業のサービス領域と、トータル費用を総合的に比較して依頼先を決めると良いでしょう。
ケース別相続税申告の料金表の具体例と料金イメージ
4000万円~1億円のモデルケース料金表 – 各遺産額帯別の料金目安と計算例
相続税申告にかかる税理士報酬は遺産総額によって大きく異なり、分かりやすい料金表で確認することが重要です。遺産額ごとの一般的な目安は以下の通りです。
| 遺産総額 | 税理士報酬の相場(目安) | 想定される合計費用 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 40万円~60万円 | 40万円~60万円 |
| 5,000万円 | 45万円~75万円 | 45万円~75万円 |
| 7,000万円 | 55万円~90万円 | 55万円~90万円 |
| 1億円 | 70万円~130万円 | 70万円~130万円 |
多くの場合、税理士報酬は遺産総額の0.5%~1%程度が目安とされています。
実際の請求額は遺産構成や相続人の人数によっても前後します。
サービス内容や追加オプションを事前に確認し、見積もりを依頼するのが安心です。
財産の種類別料金変動の具体例 – 土地・株式・現金などで料金が変わるケース
財産の内容によって税理士の負担や作業量が異なるため、料金が変わることがあります。
- 現金・預金のみの場合
- 手続きが比較的シンプルで、追加料金が発生しにくい傾向です。
- 土地・不動産を含む場合
- 土地評価や現地調査が必要となり、数万円〜十数万円程度加算されることが一般的です。
- 非上場株式を含む場合
- 企業評価等の専門的作業が発生し、追加料金となるケースが多いです。
- 保険金や有価証券
- 保険金の取り扱いや評価作業で若干の追加費用が発生します。
依頼前に保有する財産内容を整理し、事前に加算要素について相談するとスムーズです。
特殊事例の費用傾向とリスク管理 – 特急申告や相続人多数の場合の加算について
申告までの期限が短い場合や、相続人の数が多い場合には加算料金が発生します。
| 特殊事例 | 主な加算要素 | 追加費用目安 |
|---|---|---|
| 特急対応 | 申告期限が迫っている | 基本料金+20~50% |
| 相続人が4人以上 | 書類作成や調整が増加 | 1人増ごとに2万~5万円 |
| 財産評価が複雑 | 不動産・株式複数等 | 個別見積もり |
リスクを避けるため、余裕を持った依頼が最善です。加算条件は各事務所で異なるため、料金表の注意書きや相談の際に必ず確認しましょう。
依頼前に相続財産や手続き内容について可能な範囲で情報をまとめておくと、スムーズな見積もりと的確な費用シミュレーションが可能になります。信頼できる税理士選びのポイントは、料金の透明性と事前説明の充実です。
自力で行う相続税申告の可否と費用対効果
相続税申告を自分でやる手順と必要書類 – 国税庁の申告書作成コーナー活用やソフト紹介
相続税申告を自分で行う場合、国税庁の申告書作成コーナーが活用できます。このサイトでは、案内に沿って必要事項を打ち込み、申告書を作成できます。用意が必要な書類は被相続人の戸籍謄本・遺言書・財産評価書・不動産の登記事項証明書・預金や株式の残高証明書などが主です。加えて、生命保険金や年金の受給証明、相続人全員の印鑑証明書等も必要になるケースがあります。市販のソフトや相続税計算アプリを組み合わせれば、財産評価や税額試算も比較的容易に進められます。自身で進める場合は、各金融機関や自治体等から早めに必要書類を取得しましょう。
自分で申告した場合のリスクと間違い例 – 申告漏れや過大税負担の事例解説
自身で申告するケースでは、財産評価や控除の適用ミスが発生しやすいです。間違いやすい主な事例は下記の通りです。
- 小規模宅地等の特例を正しく申請できない
- 名義預金や相続財産の範囲に誤りがある
- 債務控除や葬式費用の漏れ
- 税額を安く抑えられる控除・特例の見落とし
これらのミスにより、税務調査で追加課税や延滞税が発生する場合もあります。特に不動産や非上場株式など評価が複雑な財産が含まれる場合は慎重さが求められます。申告漏れや過大に税金を納めてしまうリスクは、相続税申告の経験がない場合ほど高まります。
税理士依頼との料金表比較と効果 – 費用対効果の観点から見た選択判断
自分で申告する場合は基本的に手数料は発生しませんが、専門的知識や多くの時間が必要です。一方、税理士へ依頼した場合の費用相場は遺産総額の0.5%〜1%程度が一般的です。以下に料金を比較できる表を紹介します。
| 規模 | 自分で申告 | 税理士へ依頼 |
|---|---|---|
| 遺産総額3,000万円 | 0円(実費のみ) | 約20万~30万円 |
| 遺産総額5,000万円 | 0円(実費のみ) | 約30万~50万円 |
| 遺産総額1億円 | 0円(実費のみ) | 約50万~100万円 |
税理士へ依頼すると、控除や特例適用の正確な判断が得られ、税務署対応も代行してもらえるため、結果的に納税額やリスクの軽減につながる可能性があります。財産内容が複雑な人や、正しい申告に不安がある場合は税理士への依頼も検討がおすすめです。
相続税申告の料金表に関わる節税・控除・還付サービス
税理士報酬の経費扱いと控除のルール – 税務上の処理と申告費用控除の可能性
相続税申告にかかる税理士報酬は、原則として相続税を計算する際の必要経費として控除はできません。ただし、不動産や株式などの評価に特別な専門性を要する場合のコンサルティング費用や、登記のための行政書士・司法書士費用が発生した場合は、その一部が必要経費として計上できることがあります。相続税申告の料金表を確認すると、申告書作成費用とコンサル費用が分かれて記載される場合もあるため、明細をしっかりチェックすることが重要です。
相続税申告における主な費用の取り扱い例を以下の表でご紹介します。
| 費用の種類 | 経費算入 | 備考 |
|---|---|---|
| 税理士報酬 | × | 相続財産の控除対象外 |
| 行政書士・司法書士費用 | △ | 不動産名義変更等で一部認められる場合有 |
| 登録免許税 | △ | 登記に伴う税で一部経費化可能 |
相続税申告の料金相場を知ると同時に、費用の税務処理も押さえておくことが失敗しない申告につながります。
相続税還付の可能性と料金事例 – 還付が発生した場合の成功報酬や料金体系
相続税申告後に、過大に納付していたことが判明した場合には相続税還付の手続きが可能です。相続税還付専門の税理士事務所では、還付が成功した場合のみ報酬が発生する成功報酬型の料金表を採用しているケースも見られます。還付請求の報酬相場は、還付金額の約10%~30%程度が一般的です。
代表的な還付サービスの料金体系を表にまとめました。
| サービス名 | 料金体系 | 内容 |
|---|---|---|
| 還付コンサルティング | 成功報酬10~30% | 還付成功時のみ発生、着手金無料の場合が多い |
| 申請書類整備 | 固定費または成功報酬 | 還付請求書類の作成・提出 |
相続税還付の申請には期限があるため、気になる場合は早めに無料相談を利用して、損をしないようにしましょう。
生前対策パックなど節税支援サービスの紹介 – 生前対策で料金軽減につながるプラン例
相続税対策として、生前から専門家へ相談できる「生前対策パック」やシミュレーションサービスが注目されています。これらのパックは、相続発生前に贈与計画や家族構成の見直し、不動産評価の助言などをまとめてサポートするため、将来的な申告費用や納税額を抑えやすいのが特徴です。
多くの会計・税理士事務所では下記のような節税支援プランを用意しています。
- 生前対策シミュレーション:最適な相続プランや財産分割の方法を提案
- 生前贈与コンサルティング:贈与税の仕組みを活かした節税案をアドバイス
- 不動産評価サービス:現時点の評価額を提示し将来の税額見通しをサポート
これらのサービスを活用することで、相続税申告時の料金体制が明確になると同時に、節税効果や安心感も得られます。
相続税申告に強い税理士・事務所の特徴と選び方の実践
相続税専門税理士の見極めポイント – 実績・専門性・対応力の具体的評価方法
相続税申告を任せる税理士選びでは、専門性や経験が大切です。主な判断ポイントは以下の通りです。
・相続税申告の年間件数が多いか
・資格や経歴、専門講座の受講歴があるか
・説明が分かりやすく相談への対応が誠実か
さらに、相続税に特化した税理士は最新の税制改正や状況に応じた最適な提案ができる傾向があります。個人資産の評価、非上場株式や土地の申告経験が豊富な事務所は信頼度が高まります。問い合わせや初回相談時には、料金表や報酬相場、シミュレーションなど具体的な例を挙げて説明してもらうことが重要です。
口コミ・評判・公的認定を活用した信頼性確認 – 情報収集のテクニックと注意点
税理士選びには第三者の評価も不可欠です。インターネット上の口コミや実際の相談者の声を活用しましょう。利用者の満足度や対応の早さ、トラブル対応力なども確認材料になります。
また、公的認定や登録状況もチェックポイントです。たとえば税理士会への登録、相続専門の資格、行政書士や司法書士との連携体制などが整っていると信頼性が高まります。情報収集時は過度に高評価だけを信じず、幅広い意見を参考にしましょう。
| チェック項目 | 注意点 |
|---|---|
| 口コミ・評判 | 偏った意見に注意 |
| 税理士資格の有無 | 有資格者か公式サイトで確認 |
| 所属税理士会 | 名簿照会で客観的に判断 |
実際の依頼・相談事例から学ぶ選び方の成功例 – ケーススタディ形式で解説
実際の相続税申告の成功事例では、相続人の状況や遺産の内容に応じた適切なサポートが行われています。例えば、初回相談時に料金表や加算報酬の詳細な説明があり、見積額がはっきり提示されたケースでは、その後の手続きがスムーズに進行しています。
・土地評価など複雑な資産のある相続で、専門的な評価力をもつ税理士を選んだ結果、節税につながった
・料金相場やシミュレーションを明確に伝えてくれる事務所を選ぶことで、費用面でも納得して依頼できた
・申告期限直前でも迅速に対応してもらえたことで高く評価されたケースも多い
このように、専門性や対応力、料金説明がしっかりとした事務所へ依頼することで、安心して相続税申告を進められます。
相続税申告の料金表に関するよくある疑問と詳細解説
代表的な具体質問例を料金表と絡めて解説 – 5000万円や現金3000万の相続税はいくら?など
相続税申告で多くの方が気になるのは、実際にどれくらいの税額や税理士報酬が発生するのかという点です。遺産額ごとの概算や費用相場を把握することで、納得のいく申告準備ができます。
遺産総額と目安の税理士報酬を、分かりやすく一覧表でまとめました。
| 遺産総額 | 税理士報酬目安(税別) |
|---|---|
| 3,000万円 | 15〜25万円 |
| 5,000万円 | 25〜40万円 |
| 1億円 | 40〜60万円 |
| 2億円 | 60〜100万円 |
例えば、3,000万円の遺産の場合は15〜25万円前後、5,000万円なら25〜40万円前後が一般的な相場です。案件の複雑さや土地の評価手法、申告期限の迫り方などにより加算報酬が発生することがあります。
また、相続税自体の計算では基礎控除額3,000万円+法定相続人の人数×600万円を超えるかどうかがポイントです。例えば、子供2人で5,000万円を相続した場合、納税額は控除後の遺産額次第で異なります。
詳細な税額は国税庁の計算シミュレーションなどを活用し、正確な税額を把握しましょう。
費用負担者や支払い方法に関する疑問 – 誰が払う?タイミングは?
相続税申告を税理士に依頼する場合、報酬の支払い者や時期も気になるポイントです。
- 費用の負担者は主に申告書の名義人(遺産を取得した相続人)
- 複数の相続人がいる場合は、基本的に相続分に応じて按分されるケースが多い
- 支払いのタイミングは、申告書作成完了時や提出前、事務所ごとに分割・一括相談可
- 一部の事務所では、事前着手金や報告後の支払いを設定
また、相続税申告が不要なケースでも、相談料や一部調査費用が発生することがあるため、契約時に事前確認が重要です。行政書士や司法書士に相続関連を依頼する場合も類似した料金体系となることがありますので、事前に見積もりを取得することが安心につながります。
見積もり依頼から契約までの流れと注意点 – スムーズな申告手続きを支える基本知識
税理士への依頼から相続税申告完了までの流れは、初めての方でも混乱しないよう押さえておきましょう。
- 見積もり依頼:遺産内容や相続人情報を伝え、無料相談や見積書取得
- 正式契約:サービス内容、料金表、加算費用の有無を細かく確認
- 資料準備・提出:預金通帳、不動産登記簿、保険証券など必要書類を用意
- 財産評価・申告内容の打ち合わせ:専門家が現地調査や評価を実施
- 申告書作成・提出:完成後、内容説明の上、税務署へ申告
- 契約前には、料金体系の内訳や追加料金条件を明確にコミュニケーション
- 期限が迫っている場合は特急対応の有無も確認
- 相続手続き代行や他士業への依頼が必要な場合も早めに相談がおすすめ
専門家選びで失敗しないためには、複数社の料金表や実績・対応力も比較して、信頼できる相手に依頼することが大切です。
相続税申告の料金表のまとめと次のステップのための指針
主要な料金比較表のビジュアル化 – 料金の透明性を高める比較表の掲載
相続税申告の費用は遺産総額や申告内容の複雑さによって異なります。多くの場合、料金は遺産金額に対する割合(相場は0.5%〜1%程度)で決まることが一般的です。透明性の高い比較表を活用し、ご自身のケースに近い目安を把握しましょう。
| 遺産総額 | 報酬目安 | 加算項目例 |
|---|---|---|
| 3,000万円未満 | 20万円〜40万円 | 土地評価1件ごと+3万円 |
| 3,000万円〜5,000万円 | 25万円〜50万円 | 非上場株式+10万円 |
| 5,000万円〜7,000万円 | 35万円〜70万円 | 相続人追加1名ごと+5万円 |
| 1億円以上 | 50万円〜120万円 | 特急対応+10万円 |
料金の目安は事務所や地域によって違うため、複数社の見積もりを取り、料金体系や加算料金の発生条件まで十分に確認することが大切です。また、ご家族構成や申告内容によって、税理士や行政書士の費用にも幅があります。
手続きに必要な書類と準備チェックリスト – 申告前に用意すべき資料を整理
スムーズな相続税申告のためには必要書類が揃っていることが重要です。遅れや追加報酬を防ぐためにも、事前に以下のリストでチェックしましょう。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書や遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 預金通帳の写し・残高証明書
- 有価証券の明細
- 保険金の支払通知書
- 借入金や未払金の資料
- 被相続人の確定申告書写し
これらの資料が揃うことで、相続税の計算や必要経費の明確化にも役立ちます。土地や非上場株式などが含まれる場合は、追加で評価資料が必要となる場合があるため、早めに税理士へ相談するのが賢明です。
適正料金での申告を実現するための確認ポイント – 料金だけでなくサービス内容の吟味法
料金表は分かりやすさが大切ですが、単純な金額だけでなくサービスの質や対応範囲も重要な判断基準です。適正な料金設定かどうかをチェックするための主なポイントを確認してください。
- 基本料金と加算報酬の内訳が明確か
- 必要書類の収集・申告書作成・税務署対応まで一貫サポートか
- 相談やシミュレーションの無料範囲
- 万が一の税務調査時の対応有無
- 業務実績や実際の利用者の評判
相続税申告を自分で行う場合にも、複雑な遺産の場合は専門家のアドバイスを活用することで、時間や手間削減につながります。費用面と内容を総合的に比較し、安心して任せられる専門家を選ぶことが成功のカギです。