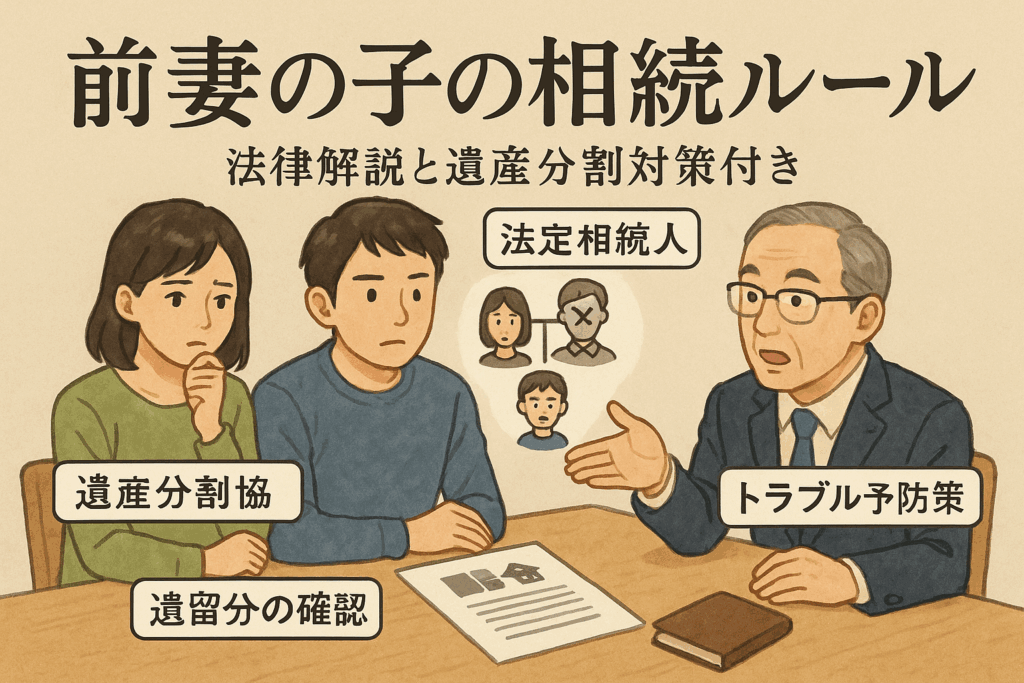「前妻にも子どもがいて、相続の手続きが思うように進まない…」。再婚・離婚が珍しくない今、相続人に前妻の子がいるご家庭は【全国で年間4万件以上】発生しています。実際、法定相続人に該当するのは「実子かどうか」という戸籍上のルールだけで決まり、離婚後も前妻の子は現配偶者の子や後妻の子と同じ相続権を法律上持ち続けます。
しかし、戸籍の調査や住所の特定、遺産分割協議での連絡ミスひとつが原因で、思わぬ遺産争い・相続放棄・不動産名義変更の遅延といった問題につながるケースが少なくありません。「連絡先がわからないと手続きが進まない」「知らない相続人から突然通知が来た」といったご相談も、弁護士事務所では【年間数千件】にも及びます。
また、2020年の民法改正以降は遺留分や相続放棄の扱いにも変化があり、対策を怠ると分割割合で大きく損をするリスクも…。この記事では、「前妻の子がいる場合の相続」を正しく理解し、押さえておくべき法的枠組みや具体的な手続き・トラブル回避策を現場データと実例をもとに徹底解説します。
「まず何から始め、どこに注意すれば損をしないのか」。最後まで読んでいただければ、ご自身の状況に合わせた最適な選択肢が見えてきます。
前妻の子が相続に関する基本ルールと最新法的枠組み
法定相続人の範囲と前妻の子が法的位置付け – 離婚後でも実子は法定相続人となる理由を具体的に解説
前妻との間に生まれた子供は、離婚後も変わらず民法上の法定相続人です。これは血縁による関係が維持されるためで、配偶者や後妻の子と同じ順位で相続権を持ちます。前妻と離婚しても、子供との親子関係に変化はなく、被相続人が亡くなった際には、前妻の子も他の子供と等しく財産分与の対象となります。
法定相続人の範囲を簡単に示すと以下の通りです。
| 相続人の順位 | 法定相続人 | 主な該当例 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 実子、養子、前妻の子 | 長男、後妻の子など |
| 第2順位 | 直系尊属 | 父母、祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 実兄弟、異母兄弟 |
前妻の子供は、第1順位の実子として扱われるため、例え親が再婚して新しい家庭を持っても、相続分の権利を完全に失うことはありません。
戸籍・認知・養子縁組が相続権に与える影響と注意点 – 戸籍・認知・養子縁組の仕組みや、実務での確認方法と事例
相続権を持つかどうかは、戸籍上の記載や認知の有無で変わります。実の子であれば必ず相続権がありますが、未認知の非嫡出子の場合、認知されていなければ原則として相続権は発生しません。また養子縁組を結んだ場合、養子も実子と同じ法定相続分を持ちます。
戸籍の確認ポイント
-
子供の出生届が提出され、親子関係が記載されている
-
認知された事実が戸籍に明記されているか
-
養子縁組の手続きが正式に完了しているか
事例
-
離婚後も親権を持たない親と実子である限り、再婚先で新たに生まれた子と同じく相続権有り
-
認知が無い場合、家庭裁判所への申立てが必要になることも
確実に相続権を証明したい場合、戸籍謄本の取得と確認が重要となります。
前妻本人の相続権と現配偶者・後妻との違い – 家族関係ごとの法的区分および適用事例
前妻には離婚成立時点で被相続人の配偶者としての地位が消失するため、相続権はありません。一方、現配偶者や後妻は、被相続人の死亡時に婚姻関係がある場合のみ、配偶者として相続人となります。
前妻の子供と現配偶者がいる場合、遺産は配偶者に1/2、残りを子供全員で等分することが一般的です。
| 事例 | 相続権の有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 前妻本人 | 無し | 配偶者ではなくなるため、権利無し |
| 前妻の子 | 有り | 実子であるため、母親の配偶者地位に関係なく権利有り |
| 現配偶者・後妻 | 有り | 被相続人死亡時に婚姻関係があれば配偶者として権利有り |
前妻の子と現配偶者・後妻・後妻の子も、法定相続分については平等です。家系が複雑な場合、相続分や手続きでトラブルを防ぐためにも、事前の準備と法的確認が重要です。
前妻の子が相続分、遺留分の仕組みと実際の割合計算
前妻の子と後妻の子が法定相続分とその根拠 – 分割割合や相続分の具体的な計算方法
再婚家庭では、前妻の子も後妻の子もどちらも法律上の相続人となります。民法により、親の死亡時における子どもの相続分は全て平等とされており、親の婚姻歴に関係なく取り扱われる点が重要です。配偶者がいる場合、配偶者が全体の2分の1を、残り2分の1を全ての子どもが均等に分け合います。
例をテーブルで示します。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 1/2 |
| 前妻の子1人 | 1/2×1/(前妻の子+後妻の子の合計人数) |
| 後妻の子1人 | 1/2×1/(前妻の子+後妻の子の合計人数) |
このように、前妻の子も、後妻の子も法定相続分において差がありません。相続分の計算では子どもの人数がポイントとなるため、戸籍の調査が不可欠です。
遺留分とその割合、前妻の子がへの影響 – 遺留分の意味や権利発生条件、請求事例
遺留分とは、法定相続人が最低限保持できる遺産の割合です。遺言によって「財産を全て後妻の子に」と指定された場合でも、前妻の子には遺留分の主張が可能です。
遺留分の割合は下記の通りです。
-
配偶者と子がいる場合:法定相続分の1/2
-
子のみの場合:法定相続分の1/2
-
配偶者のみ、または直系尊属のみ:法定相続分の1/2または1/3
遺留分を行使するには、亡くなった日から1年以内に意思表示が必要です。前妻の子が遺言によって除外された場合もこの制度で最低限の財産を請求できます。実際には「遺留分侵害額請求書」を提出し、協議や調停で解決する例が多く見られます。
遺産分割協議の進め方と割合の調整方法 – 話し合い・調停の実際の流れや留意点
遺産分割協議は、全ての法定相続人が参加し合意が必要です。前妻の子と連絡が取れない、居場所が分からないケースも多く、その場合は家庭裁判所を利用して「不在者財産管理人」の選任などの手続きを進めることができます。
進め方の基本は以下の通りです。
- 戸籍謄本の収集により全相続人を確定
- 相続財産の調査と評価
- 全相続人との協議・合意(必要なら手紙や電話で連絡)
- 合意困難時は家庭裁判所で調停申立て
協議書作成後は、不動産の名義変更や銀行口座の解約なども全員の署名・押印が必要です。トラブル回避には事前の情報共有や専門家へ相談することが推奨されています。
前妻の子がに関する相続トラブルの実例と回避策
連絡しない場合の法的リスクと注意事項
前妻の子が相続人であるにもかかわらず、相続開始時に連絡をしない場合、複数の法的リスクが生じるため注意が必要です。まず、相続財産を分割するには対象となるすべての相続人が協議や手続きに参加しなければなりません。前妻の子に対して連絡しないまま協議を進めたり、不動産を名義変更した場合、後日発覚時に分割協議自体が無効とされるケースや、相続不動産の登記ができない問題が発生します。
主なリスクと注意事項を整理すると、以下の通りです。
| リスク内容 | 具体的事例 |
|---|---|
| 相続手続の無効化 | 前妻の子を除外した場合に、遺産分割協議が無効になる |
| 不動産名義変更の支障 | 所有権移転登記ができず、不動産売却などが不可能になる |
| 損害賠償請求や法的紛争のリスク | 発覚後、前妻の子から損害賠償請求や調停の申し立てが可能 |
このようなトラブルを避けるため、全相続人への速やかな通知と正しい手続きが不可欠です。
連絡先不明・所在調査の方法
前妻の子の居場所や連絡先が分からない場合でも、安易に放置することはできません。相続人全員の協力が手続きの要件となるため、必ず所在調査を行いましょう。戸籍や住民票を基に現住所が判明するケースが一般的ですが、転居や失踪などで情報が古い場合もあります。
調査のステップをまとめると次のようになります。
- 被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人の本籍地や住所を確認する
- 住民票の写しや戸籍附票を利用して、転居履歴を辿る
- 居所不明・音信不通の場合、市町村役場や関係機関で最新情報を調査
- 調査でも判明しない場合は、行政書士や弁護士など司法専門家に依頼
相続人の所在調査をしないまま進めると手続き全体がストップし、先延ばしや再手続きの原因となるため、可能な限り早めに調査や連絡を実施することが大切です。
連絡拒否や返答無視のケースの実務対応法
前妻の子が相続の連絡に応じない、手紙や電話への返答を無視する場合も、相続手続きを進めるうえでは適切な対応が求められます。こうしたケースでは家庭裁判所への調停申立や、不在者財産管理人の選任を活用できます。
以下の対応法が現実的です。
-
調停申立:家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、裁判所が関与する形で話を進める
-
不在者財産管理人:居所不明の場合、財産管理人を選任して相続手続の代理を依頼する
-
書面記録の保存:連絡した履歴や通知文書の控えを保管し、トラブル時の証拠とする
こうした対応を取ることで、無視や拒否があっても法定通り手続を継続できるようになります。実際のトラブル回避には、専門家への相談や適切な法的サポートの活用も有効です。
前妻の子が相続させないための法的手段とその限界
遺言書の書き方と効力を持つための要件 – 有効な遺言書作成の手順と注意点
前妻の子の相続を制限するには、有効な遺言書の作成が重要です。遺言書には民法で定められた形式が存在し、不備があると効力を失うため、下記の表で確認しましょう。
| 遺言書の種類 | 作成方法 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・署名を自筆 | 押印が必要。不動産等は特定できる明記 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で証人2名立会 | 形式不備や偽造リスクが少なく、安全かつ確実 |
| 秘密証書遺言 | 書いた内容を封印し公証役場で手続き | 内容不備に気をつけ、署名・押印・公証必須 |
注意点として、遺言書が無効となる主な例:
-
日付や署名の欠如
-
財産の特定が不十分
-
遺言能力(15歳未満、判断能力欠如など)の欠如
遺言書を使うことで前妻の子への相続配分を調整できますが、遺留分の保護があるため、完全に権利を奪うことはできません。
遺留分放棄や相続放棄、相続人廃除の手続きと注意点 – 裁判例や審査条件を交えて詳述
前妻の子の相続分を大幅に減らしたい場合、法的に取り得る手段には遺留分放棄・相続放棄・相続人廃除があります。
- 遺留分放棄
- 家庭裁判所の許可が必要
- 生前に合意があっても手続きが未完成だと無効
- 相続放棄
- 相続発生後3カ月以内に家庭裁判所へ申述
- 一度放棄すると撤回不可。他の相続人の負担増に注意
- 相続人廃除
- 被相続人(生前)や遺言執行者(死亡後)が家庭裁判所へ請求
- 「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」など厳格な要件および裁判所の認定が必須
ポイント
-
遺留分侵害額請求は、遺留分を受け取る権利のある前妻の子が起こせます。
-
裁判所の判断によるため、感情的理由だけでは認められません。
注意点:手続きには法的根拠が必要であり、書面や証拠準備、裁判所の審理を経ることになります。
不動産や保険金の扱いに関する具体的注意点 – 財産ごとの分配方法や誤りやすい実例
前妻の子が相続対象になる主な財産は、不動産・預貯金・金融資産・生命保険金です。財産種類により分配方法や注意点が異なります。
| 財産の種類 | 分配・指定方法 | 注意点・誤りやすいポイント |
|---|---|---|
| 不動産 | 遺言書・遺産分割協議 | 固定資産の名義変更に全相続人の同意が必要 |
| 預金・証券 | 銀行手続き・協議 | 相続人全員の署名・実印と印鑑証明が必要 |
| 生命保険金 | 受取人指定 | 保険金は原則相続財産外、指定方法のミスに注意 |
| 家財・動産 | 協議・遺言書による | 実物の確認・査定と分配の合意が不可欠 |
-
不動産の場合、前妻の子の居場所が不明や連絡が取れない場合、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任が必要となることもあります。
-
保険金は受取人の指定により相続対象外とすることも可能ですが、「相続させない」ためには確実な受取人指定が求められます。
-
家や土地などを特定の人に取得させたい場合、遺言書の表現や登記手続きに注意してください。
前妻の子がと遺産分割協議の実務的進め方と通知義務
離婚や再婚が家族構成を複雑にする場面では、前妻の子が相続人となる場面も多く見受けられます。前妻の子も法定相続人であり、遺産分割協議や手続きの際、適切な通知と合意形成が不可欠です。こうしたケースでの実務的な進め方や注意点を確認しておくことが、のちの相続トラブル予防にもつながります。特に全員の相続人へ正しく通知し、迅速かつ公正な協議を進めることが重要です。
面識のない相続人への連絡方法と手紙の書き方 – 書類通知の文面例や心理的配慮
前妻の子と面識がない場合や音信不通の場合でも、遺産分割協議には必ず連絡が必要です。連絡が取れないままだと遺産分割の手続きが進まず、財産管理や相続登記に支障をきたします。
下記のポイントを重視しましょう。
-
必ず戸籍や住民票で現住所を特定し、確実な連絡先を把握する
-
手紙で通知する場合、差出人・被相続人との関係・遺産分割協議の趣旨を明確に記載する
-
配慮として、突然の通知に驚かないよう、丁寧な文体や前置きを用意する
-
内容証明郵便等で記録を残すことも検討する
通知文面例:
| 件名 | 遺産分割協議についてのご連絡 |
|---|---|
| 文章例 | このたび○○(故人)の相続に関し、法定相続人である○○様にご連絡差し上げます。遺産分割協議のため一度ご連絡いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。ご不明点はご質問ください。 |
突然の書類に対し、心理的な配慮を忘れずに連絡することが信頼関係の第一歩になります。
遺産分割協議に必要な書類と証明書類一覧 – 戸籍謄本・遺産目録などの準備方法
遺産分割協議を円滑に進めるには、正確な書類の準備が不可欠です。主な必要書類を以下の表にまとめます。
| 書類名 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本一式 | 相続人全員の確認 | 被相続人の出生から死亡まで・相続人全員分 |
| 遺産目録 | 相続財産の内容と評価 | 不動産・預貯金・有価証券など一覧化 |
| 被相続人の住民票の除票 | 死亡した事実の証明 | 市区町村で取得 |
| 相続人の印鑑登録証明書 | 遺産分割協議書の押印用 | 発行日から3カ月以内が原則 |
| 遺産分割協議書 | 合意事項の記録 | 相続人全員の署名押印が必要 |
被相続人の戸籍を出生からすべて取得することで、漏れのない相続人特定ができます。財産目録は、不動産の場合は登記事項証明書、預金や証券類は残高証明書などで確認し、漏れや誤記載に注意しましょう。
合意形成のポイントと紛争予防策 – 交渉や弁護士の利用に関する助言
遺産分割協議の合意形成には、全相続人の納得と公平性が必要です。過去の関係や再婚事情から生じる感情的対立にも配慮しつつ議論を進めるのが得策です。
合意形成を円滑にするための重要なポイント
-
すべての相続人に、遺産の全容と分割案を透明に提示する
-
事前に全員が話し合いの場を持ちやすい日程や方法(面談・書面・Web会議など)を調整する
-
感情的な衝突が生じそうな場合や進行が難航する際は、第三者(弁護士や司法書士)のサポートを利用
-
相続人の一部が連絡不通の場合は、家庭裁判所での調停や不在者財産管理人の選任など、法的措置も検討
専門家のサポートを得ることで、複雑な法律問題や感情面のトラブルを未然に防ぎ、公正かつ確実な相続手続きが可能となります。
複雑な家族関係例:前妻の子がと後妻の子の相続パターン別対応
前妻の子がと後妻の子が相続分・関係性の法律的整理 – 兄弟姉妹間の相続権や分割具体例
前妻の子と後妻の子は、いずれも民法上で同等の法定相続権を持ちます。婚姻中の実子・非嫡出子で区別はされず、前妻との子も後妻との子も法定相続人となります。もし相続人が「配偶者」「前妻の子2名」「後妻の子1名」であれば、配偶者は全体の2分の1、3人の子は残りの2分の1を人数割りします。具体的な分割例は以下の通りです。
| 相続人 | 相続分の割合 |
|---|---|
| 配偶者 | 1/2 |
| 前妻の子1 | 1/6 |
| 前妻の子2 | 1/6 |
| 後妻の子 | 1/6 |
このように、前妻の子に連絡せず協議を進めても法的に無効となるため、全相続人への通知が必須です。不動産や現金などすべての財産分割において、公平な権利が保護されます。
再婚や養子縁組による相続権の変化と対応策 – 養子縁組や再婚で変わる相続人の整理
再婚や養子縁組を行うことで、相続人の範囲に変化が生じます。再婚した場合、前妻の子も後妻の子も法定相続人となり、相続分は平等です。一方、新たに養子縁組をした場合、その養子も実子と同じ法定相続分を持ちます。
相続関係を整理するには、以下のポイントに注意が必要です。
-
前妻の子は養子縁組しなくても法定相続人
-
配偶者の子が戸籍に入っていない場合、戸籍調査が必要
-
後妻の子だけが養子縁組された場合でも、前妻の子の相続権は消失しない
-
養子の人数による“法定相続分”の変動に備えること
書類の整備や戸籍謄本の確認を行い、相続人の範囲を明確にしたうえで遺産分割を進めることがトラブル回避に直結します。
複雑家族における相続トラブル回避の交渉術 – 実際のトラブル例と問題回避の工夫
前妻や後妻の子が関与する相続では、連絡が取れない、音信不通、財産分割で合意が得られないといったトラブルが多発しやすいです。典型的な問題点は下記の通りです。
-
前妻の子に相続の連絡をせずに遺産分割を進めてしまった
-
前妻の子が相続放棄をしなかったため協議が難航した
-
相続人の居場所がわからないことで手続きが進められない
このような場合、手紙や書類で正式に連絡を取り、丁寧かつ法的根拠を示した通知が重要です。連絡手段が分からない場合は戸籍の追跡調査や弁護士・司法書士への依頼が効果的です。
相続放棄や遺留分対策を含め、必要に応じて早期に専門家へ相談し、遺言書の作成や財産の生前整理を進めることで、更なる争いを未然に防げます。円滑な相続にはコミュニケーションと法的対応のバランスが不可欠です。
財産種類別の相続手続きと前妻の子が権利行使
不動産名義変更と共有問題の実務ポイント – 不動産の名義変更に関する法律と手続き
前妻の子が相続人となる場合、不動産の名義変更が不可欠です。不動産は遺産分割協議がまとまるまでは全相続人の共有財産となるため、前妻の子にも明確な権利があります。名義変更手続きには、法定相続分または協議で決定した割合が登記されるため、前妻の子も権利行使が可能です。
所有権移転登記の流れは以下の通りです。
- 戸籍謄本や遺産分割協議書など必要書類を全員分用意
- 登記申請書の正式な作成と提出
- 各相続人が実印で協議書に押印し、印鑑証明書を提出
「前妻の子 相続 不動産」や「前妻の子 相続権」といったワードで多くの疑問を持たれるのが、前妻の子が連絡に応じないケースです。こうした場合も、全相続人の署名捺印または家庭裁判所による調停が必要となります。
| 必要書類 | 概要 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 前妻含む全相続人分が必須 |
| 遺産分割協議書 | 全員の署名・実印 |
| 印鑑証明書 | 被相続人死亡時点で現存するもの |
金融資産・預貯金の凍結解除と引き出し手続き – 銀行・証券会社での手続き方法
被相続人が銀行や証券会社に資産を持っていた場合、死亡後は即座に口座凍結となり、相続人全員の同意がなければ預貯金の払戻しや解約ができなくなります。前妻の子も相続分を請求できるため、連絡先が不明な場合は金融機関に対して戸籍を提出し、法定相続人であることを証明する必要があります。
主な手続きの流れは以下となります。
-
相続発生後に銀行へ死亡届を提出
-
金融機関から指定書類を受領(相続届・印鑑証明・戸籍等)
-
遺産分割協議書が整った時点で分配・解約を実行
相続人の一部が相続放棄を選択した場合、その証明書も提示が必要です。不明点がある場合は、弁護士や司法書士への相談が有効です。
| 手続き | 主な書類 | 前妻の子の注意点 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 戸籍謄本、本人確認書類 | 戸籍上の関係が必須 |
| 相続届 | 全相続人の署名/押印・印鑑証明書 | 連絡後、同意取得が必要 |
| 払戻依頼 | 協議書・審判書・放棄証明等 | 権利主張も手続き可能 |
生命保険の受取人指定と相続への影響 – 生命保険特有の手続きと注意点
生命保険金は、一般的に「受取人」に直接支払われます。このため、遺産分割協議の対象とならない場合が大半です。受取人に前妻の子が指定されていれば、その子が速やかに保険金を請求できます。
ただし、保険金が法定相続分を著しく上回る場合、他の相続人から遺留分減殺請求などの異議を申し立てられることがあります。これは特に「前妻の子に相続させない方法」や「前妻の子 相続放棄」といったニーズに直結します。
主な注意点は以下の通りです。
-
受取人が明記されていない場合、相続財産として全員で分けることになる
-
相続税の課税対象となるため、申告漏れに注意
-
遺留分の侵害に該当する場合、他の相続人から法的請求を受ける可能性
| 保険の種別 | 主な手続き | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 生命保険 | 受取人に直接請求 | 受取人指定が最優先 |
| 死亡保険 | 保険会社へ死亡申告等 | 相続財産になる場合あり |
| 相続税申告 | 税務署での手続き | 非課税限度額に注意 |
このように、前妻の子が関与する相続では、財産ごとに異なる手続きや書類の準備、相手との連絡が不可欠となります。権利行使にあたっては早めに準備を進めることが大切です。
前妻の子が相続に関するQ&A集:実務でよくある疑問を厳選収録
重要な法的疑問と回答 – 実際の現場で多い疑問点への明快な説明
以下のテーブルは、前妻の子の相続問題で特に相談や質問が多い主なトピックとその答えを整理したものです。
| 疑問 | 回答 |
|---|---|
| 前妻の子は法定相続人になれますか? | はい。 前妻の子も後妻の子や配偶者と同じく、法律上の相続人です。父母が離婚していてもその権利は変わりません。 |
| 前妻の子の相続分はどのくらいですか? | 相続分は均等。 例えば配偶者と子2人(前妻の子1名・後妻の子1名)なら、配偶者1/2・子ども1/4ずつとなります。 |
| 連絡がつかない前妻の子がいる場合、相続手続きはどう進めるべき? | 相続手続きには全相続人の協力が原則必要です。連絡が取れない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てるなどの法的対応を検討します。 |
| 前妻の子に相続させない方法はありますか? | 完全に排除することは困難です。遺言書で調整や相続放棄のお願いは可能ですが、最低限の遺留分は法律で保障されています。 |
| 前妻の子の遺留分の割合は? | 子供の遺留分は法定相続分の半分です。例えば子が一人なら全遺産の1/4が遺留分となります。 |
ご家族の状況によって手続きや対応が異なるため、正確な戸籍調査も必要となります。
実務的トラブルへの対応策と専門家活用の案内 – 問題発生時の対応と専門家の利用案内
相続をめぐるトラブルは現実的に多発しています。特に前妻の子と現家族間でのコミュニケーション不足や、連絡の行き違い、不動産や預貯金の分配に関する認識違いが多くみられます。以下のようなケースでは、早めの対応と専門家のサポートが有効です。
-
トラブルの主な例
- 連絡が取れない相続人がいる
- 無断で遺産の一部を処分してしまった
- 遺産分割協議がまとまらない
- 前妻の子が所在不明、不動産の相続登記が進まない
-
解決策として有効なアクション
- まずは戸籍と相続人調査を正確に行い、全員と連絡を取りましょう。
- 面識のない相続人には、敬意を持った手紙(例:挨拶と相続手続き協力依頼を明記)でアプローチします。
- 連絡がどうしても取れない場合は、不在者財産管理人の選任申立てなどを家庭裁判所に依頼できます。
- 遺言書がある場合、その執行と遺留分配慮の確認も必須です。
-
専門家活用のメリット
- 複雑な法的対応や分割協議の進行は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家への依頼が安心です。
- 遺産に不動産が含まれる場合、登記や評価の専門知識も求められます。
- 豊富な経験を持つ専門家は、相続トラブルの予防策やスムーズな解決をサポートしてくれます。
確実な権利保護のため、専門家の無料相談やサービスも積極的に活用することで、不安なく相続手続きを進められます。